身近なモノから、世界がみえてくる。驚きの連続に、子どもたちが弾みだす。
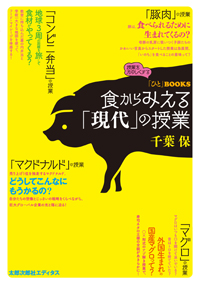
食からみえる「現代」の授業
- 発行日
- 2011年03月発行
- 判型
- A5判・並製
- 頁数
- 160ページ
- 価格
- 本体1800円+税
- ISBN
- 978-4-8118-0744-7
- Cコード
- C0037
「知る喜び」に子どもが弾みだす授業をつくる。深くて 楽しい授業を追求してきたベテラン実践家たちが、いま、 ほんとうに必要とされている授業づくりの発想法と実践 記録を開示します。
いま、学校に若い教師が増えてきました。団塊の世代が退職期を迎えて、世代交代が進みつつあります。さらに安上がりな教育行政の影響で、臨時的任用や非常勤採用などの非正規雇用の教師も大幅に増えています。
また教師たちには、計画書や報告書の作成などのいわゆる雑務が増加し、教材研究の時間や、子どもとふれあう時間も十分確保できない状況が現出しています。そのうえ学校には職階性がもちこまれ、強化されました。その結果、先生たちの連帯の力が削がれ、授業づくりにおたがいの知恵をだしあう同僚性も失われてきています。
また、文部科学省は、全国統一テストによる各県の順位を公表しました。その影響で、多くの県で順位を上げろという声が強まりました。その後、統一テストが任意参加になったにもかかわらず、参加表明する市町村があいついでいます。教師たちは、成績を上げるよう努力をさらに求められ、いままで以上に暗記と習熟に専念するよう、駆りたてられてもいます。
一方、子どもたちには「ゆとり教育」の反動から、学習時間の増加が図られ、学校での生活も長時間になりました。
心ある教師が、東アジア型教育を乗り越えようと、対話を重視したグループでの学びあいに取り組む姿が、全国教育研究集会で報告されました。しかし全国的には、黒板に向かっての暗記と習熟型の東アジア型教育が支配的で、そこからの脱皮には課題が山積しています。
![]()
いま子どもたちに必要なのは、受動的にあたえられたことを覚える「勉強」から脱して、知的好奇心をもって活動的な「学び」を実現することではないでしょうか。
『ひと』誌は、1973年の創刊から、学ぶ者の視座にたって教育を考えるオールタナティブな実践を生みだす努力を続けてきました。『ひと』誌に多くの先進的な授業実践者が集い、授業を発表してきました。
『ひと』誌は一貫して、学校や教育の閉塞にたいして、人間・社会・市民の常識にもとづいて新鮮な空気をおくりつづけてきました。
そこで蓄えた授業の知的エネルギーを、いまこそ、混迷を深める教師たちに、社会や市民にも、手渡す必要があると感じます。
木々は寒さや暑さに耐え、年輪を刻みながら成長し、やがて巨木に育ちます。
教師も、子どもたちも、わくわくするような「知」の授業体験を積み重ねて、「知の年輪」を増やし、大きな巨木に育ってほしいと願っています。
このシリーズが、そのお役に立てることを祈念します。
「ひと」BOOKS編集委員会
身近なモノから、世界がみえてくる。驚きの連続に、子どもたちが弾みだす。
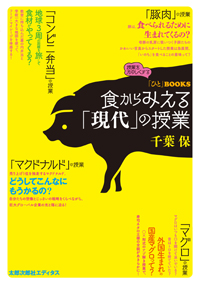
新発見の連続に、教室中がハラハラ・ドキドキ。子どもが歴史家の顔になる。
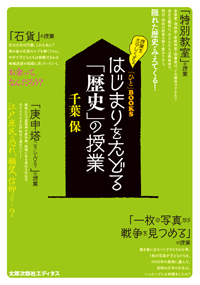
子どもたちの疑問に向きあい、ともに学ぶ。3.11後を生き、未来を選びとるために。
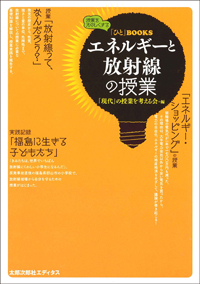
物語教材から俳句が生まれる。だれでもできる俳句の授業。
