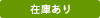竹内洋岳最新刊にして、山岳書初(!)の「下山」ドキュメント
ヒマラヤ8000m峰14座完全登頂とは、14の山すべての頂から無事に下ってくるということ。「生きて還ってこなければ、下山しなければ、登山ではない」とつねづね語り、それを実現してきた竹内は、どのように山を下ってきたのか。疲労困憊のなかで頻発する危機、生死を分けた判断と行動、朦朧とする頭で考えていたこと……。敗退もふくめて、17年にわたる14座の全下山をたどり、現在に続く新たな挑戦を報告する。
世界的クライマー、ラルフ・ドゥイモビッツはじめ、本人を深く知る6人へのインタビューをとおして竹内洋岳を「解剖」するコラムも収録。
はじめに 頂上に着いただけでは終わらない
標高8000m を超える世界は「デスゾーン」と呼ばれます。そこは文字どおり、生命の痕跡すら感じない場所。私たちが続けてきた登山は、そのデスゾーンへ足を踏みいれ、登頂し、なんとか生きて帰ってくる、そのくり返しでした。大切なのは登頂することではなく、登頂して無事に帰ってくることです。
頂上はゴールでも折り返し地点でもありません。登山の行程はひとつの「輪」のようなものです。頂上が輪のどこに位置するかは、ゴールしてはじめてわかること。頂上は地形的な最高地点ですが、登山という行為のピークは、かならずしも頂上ではありません。登山をひとつの輪と考えたとき、「登り」と「下り」は一体で、分ける必要もない。「登頂した」と言えるのは、頂上に着いたときではなく、ベースキャンプに帰ってきたときだと考えています。
一方で、登山をテーマにした本やドラマで、下山の行程に光が当たることはあまりありませんでした。登頂をクライマックスとして物語が語られていく。たしかに、「山頂」はだれにとってもわかりやすい「ゴール」でしょう。しかし、じっさいに登山をしていると、山頂がゴールだと思うことはありません。
私はよく、8000m 峰の登山を、底が見えない深い沼や池に潜ることに例えます。息を止めて水底まで潜っていき、息が続くうちに水面に浮上してくる。水底に達したからといって息はつけない。8000m 峰の頂上も同じです。着いたあとはあわてず、しかしスピーディーに、パニックにならないよう自制して、エネルギーが残っているうちにBCまで帰ってこなければなりません。息が続くうちに帰ってこなければならない下山中は、ゆっくりと記録をつけることすら許されないことがほとんどです。記録の少なさも、これまで下山に光が当たらなかった一因かもしれません。
登山では「リタイア」ができません。どんなに苦労して登頂しても、あるいは途中であきらめるとしても、かならず自分で下山しなければならない。だから、「降りてくる」という行為は重要で尊いものです。降りてくるからこそ、つぎの登山ができる。下山はつぎの登山への準備であり、助走でもあるのです。
Ⅰ▼「役割」(大規模登山隊)から「愉しみ」(少数精鋭チーム)へ
1995年 マカルー[1座目] 8000m峰初下山
1996年 エベレスト[2座目] デスゾーンからの逃避
1996年 K2[3座目] ベースキャンプへの「登頂」
2001年 ナンガパルバット[4座目] 切りひらいていく下山
Ⅱ▼クライマックスとしての下山
2003年 カンチェンジュンガ[敗退] ホワイトアウトのなかを
2004年 アンナプルナ[5座目] 二度と行きたくない山
2004年 ガッシャーブルムI峰[6座目] 身近にある死
2005年 シシャパンマ[7座目] ぐるり1周旅の締めくくり
Ⅲ▼生還するために
2005年 エベレスト[敗退] 死後の帰還
2006年 カンチェンジュンガ[8座目] 見失った帰路
2007年 マナスル[9座目] 灼熱のラッセル地獄
2007年 ガッシャーブルムII峰[敗退] 雪崩に飲みこまれて
Ⅳ▼ヒマラヤへの復活
2008年 ガッシャーブルムII峰[10座目] つぎの山への登り
2008年 ブロードピーク[11座目] 激痛と落石の恐怖
2009年 ローツェ[12座目] もっともつらい下り
Ⅴ▼14サミット完全下山
2010年 チョ・オユー[敗退] 新たなパートナーと
2011年 チョ・オユー[13座目] 幻覚のなかの軌道修正
2012年 ダウラギリ[14座目] 極限の夜を超えて
つぎの山へ——14サミッターの現在地
▼インタビュー
「登山家の突然変異」——シューフィッター 釣巻健太郎の視点
「妥協なき道具マニア」——登山用腕時計開発者 牛山和人の視点
「強くて繊細なlovely person」——14サミッター ラルフ・ドゥイモビッツの視点
「スマートな野心家」——医師 柳下和慶の視点
「つかまえちゃダメな人」——山岳気象予報士 猪熊隆之の視点
「つねに帰り道を知っている人」——山岳カメラマン 中島健郎の視点